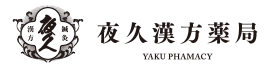はじめに
「朝起きられない」「立ち上がるとふらつく」「学校に行けない」――
こうした症状を抱える子どもたちが、近年増えています。その背景には、**起立性調節障害(OD: Orthostatic Dysregulation)**という自律神経の乱れによる疾患が隠れていることがあります。
現代医学でも少しずつ認知されてきているこの病態に対し、漢方薬ができることは何か。
今回は、漢方相談薬局の視点から、起立性調節障害の特徴と、その改善を助ける漢方薬について考えてみたいと思います。
起立性調節障害とは?
起立性調節障害とは、起立時の血圧調整がうまくいかず、脳の血流が不足することでめまいや倦怠感が起こる状態です。特に10代前半の子どもに多く、思春期の発達やストレスが大きく影響します。
主な症状:
- 朝起きられない、午前中に調子が悪い
- 立ちくらみやふらつき
- 動悸、息切れ
- 頭痛、食欲不振
- 集中力の低下、イライラ、不安感
原因として考えられるもの:
- 自律神経の未成熟
- 心身のストレス
- 過度な学業やスマホ使用などの生活習慣
- 成長ホルモンの変化
漢方医学からみた「起立性調節障害」
漢方では、起立性調節障害を一つの病名として扱うのではなく、「証(しょう)」=体質と症状の組み合わせで捉えます。
例えば、次のようなタイプに分けて考えることが多いです。
① 気虚(ききょ)タイプ:
体力が乏しく、だるさが強いタイプ
→「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」「十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」など
② 気滞(きたい)タイプ:
ストレスを感じやすく、情緒不安定なタイプ
→「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」「加味逍遥散(かみしょうようさん)」など
③ 陰虚(いんきょ)タイプ:
ほてりや口の乾きがあり、寝つきが悪いタイプ
→「滋陰降火湯(じいんこうかとう)」「天王補心丹(てんのうほしんたん)」など
④ 痰湿(たんしつ)タイプ:
むくみや頭重感、消化不良があるタイプ
→「苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)」「半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)」など
実際の相談現場から
ある中学生のケースをご紹介します。
「朝になるとお腹が痛くて動けない。でも病院では異常なし。夜は元気だけど朝になると起きられない」
この子は、体格は細く、舌は淡く、脈は沈細。お腹が冷たく、ストレスに敏感。
→ 約3週間で午前中の起床が可能になり、通学も再開できるようになりました。
なぜ漢方が効くのか?
漢方の強みは、「病名」ではなく「人」を診ること。
一人ひとりの心身の状態や生活背景に合わせて、その人に合った治療を行うため、心理的な不調を抱える子どもたちには特に相性が良いと言えます。
また、体にやさしく、長期的に使える処方が多いため、心と体の成長を支える力になれるのです。
まとめ
起立性調節障害は、ただの「怠け」ではなく、**自律神経のバランスを崩した「体の悲鳴」**かもしれません。
漢方薬は、そうした子どもたちの声なきSOSに、寄り添い支える選択肢の一つです。
お子さんの「なんとなく調子が悪い」が続くとき、ぜひ一度、漢方的な視点からのアプローチも取り入れてみてはいかがでしょうか?
漢方相談はお気軽に
夜久漢方薬局・夜久鍼灸院では東洋医学の視点からあなたに合った漢方薬、鍼灸治療を提案し身体の状態を調えお悩みの不調を改善へ導きます。自律神経失調症、婦人病、慢性疼痛、痺れなどでお困りの方は、漢方専門の夜久漢方薬局へご相談ください。
夜久漢方薬局は完全予約制となっております。ご来局の際はご予約をお願い致します。
予約電話番号:079-677-0056 予約可能時間:9時~19時(日曜・祝祭日は休業)
夜久漢方薬局公式ラインからでもご予約可能です。以下QRコードをラインアプリでスキャンして頂ければ友達追加できます。

夜久漢方薬局・夜久鍼灸院 院長 夜久公也